【取材記事】BtoB×グローバルでFacebookページを運用するポイント・工夫とは?
2016/10/19

欧米やアジアなど、世界120カ国、900都市、3,000拠点を展開する世界最大のレンタルオフィスプロバイダー「リージャス」。世界中の企業、ビジネスマンをターゲットとして事業を展開する同社は、Facebookページを既存顧客向けの情報発信だけでなく、新規顧客の開拓にも活用しています。
主要なマーケティングチャネルとしてFacebookを選択した背景や、他国と共同でFacebookページを運用するうえで工夫している点などを、運用担当の川崎様にお伺いしました。
Interview / ソーシャルメディアラボ編集長 大久保亮佑
- 目次
- インバウンドで効率よく見込み顧客を開拓!Facebookページの役割
- グローバルとローカル、既存と新規、あらゆるバランスを考慮してコンテンツを設計
- 現状の課題とこれからの展開
インバウンドで効率よく見込み顧客を開拓!Facebookページの役割
世界各国の拠点とFacebookページを共有し、情報を発信。国と言語をターゲットとして設定することで、地域別の情報と全世界共通の情報を同一ページ内で管理・運用している。
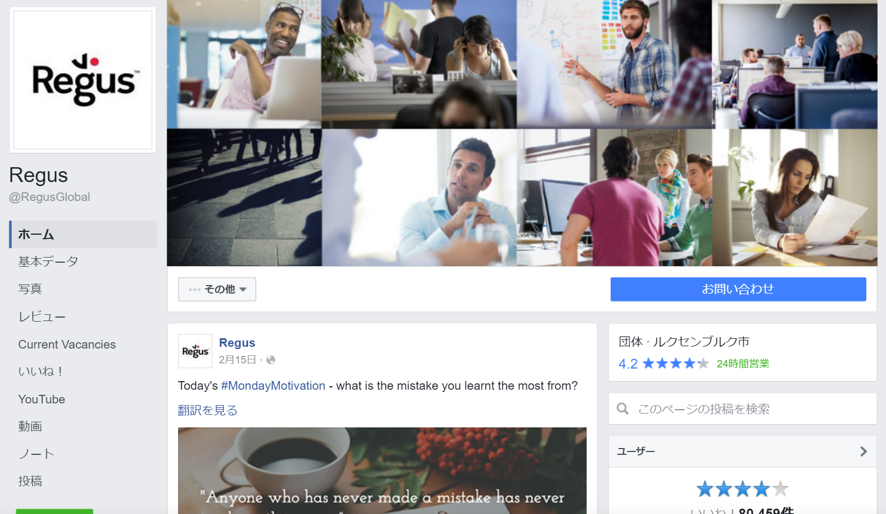
Facebook活用の背景
大久保:Facebookを活用し始めた背景を教えてください。
川崎氏(以下敬称略):主な理由は2つです。1つ目はレンタルオフィスやコワーキングなどのニーズが生まれて能動的に探し始めたユーザーをインバウンドで獲得するため、2つ目はレンタルアフィスやコワーキングに対する認知がない潜在層にもアプローチするためです。
大久保:インバウンドで獲得するための活用ですか。
川崎:はい、弊社の主なお客様はスタートアップや、期間限定のプロジェクトなど、固定のオフィスを借りるよりもフレキシブルにオフィスを使いたいという方です。そのようなニーズが生まれるタイミングは限られているので、こちらからアウトバウンドでアプローチするのは効率が悪い。しかしながらニーズがある人は積極的に情報を収集するので、ソーシャルメディア含めたいろいろな場所で見つけてもらえるような施策を重視しています。
大久保:2つ目の潜在層へのアプローチに関してもお聞かせください
川崎:潜在層に対して広告を打つのはなかなかターゲティングが難しく、費用対効果が合いにくい部分があります。なので弊社としてはソーシャルメディアのような、口コミが広がりやすいところで情報発信をして、ユーザーさんの間で広がっていったらと思っています。そのためのわかりやすいプラットフォームとしてFacebookページが機能していると思います。
口コミ経由の問い合わせが圧倒的に多い。Facebookを運用してみて感じる効果
大久保:実際にFacebookページを日本の担当者として運用してみて、数値面でもそれ以外の面でも効果を感じますか?
川崎:まずFacebookページを始めてから、全体のインバウンドの問い合わせ数が増えました。直接的にFacebookから流入してきたユーザーがコンバージョンしているかというとそれは見えにくい部分もありますが、影響はあると思いますね。
また、実際に問い合わせてくださるお客様の中で、知人・友人の紹介や知っている方が使っていたという方のパーセンテージが非常に高いので、口コミの広がりという面でもFacebookページの効果があると感じています。
特にビジネスラウンジやバーチャルオフィスなどのサービスの利用者が増えたのは、ソーシャルメディアを通じた個人間の口コミの影響が大きいのかもしれません。問い合わせをくださるお客様の幅が広がったのは非常にうれしい変化です。
グローバルとローカル、既存と新規、あらゆるバランスを考慮してコンテンツを設計
多言語Facebookページ運用の難しさ
大久保:御社のFacebookページでは、日本語の言語ターゲティングでの投稿と英語の投稿、どちらも流れていますよね。海外との連携はどのようにされているのでしょうか。
川崎:リージャスグループ全体として発信したいものに関しては、言語ターゲティングをせずに投稿されます。コンテンツの内容は事前に共有されていますが、全体として直接的な宣伝というよりは、顧客層に合わせたビジネス情報や親近感を感じていただけるようなものがメイン。リージャスのファン層を広げることを意図しています。
特に力を入れているのが、マイストーリーというものです。リージャスのお客様には起業家の方が多いので、グローバル本部が定期的にインタビューをしてコンテンツを作ってくれるんです。例えばロンドンでAさんという方がどのような方法で起業して成功していったか、などを紹介しています。
そういったものを各国で準備するというのはかなり大変ですが、グローバルが1つのコンテンツを用意して、各国がそれを適宜使えるようになっています。それらをベースとして、各国の情報を投稿しています。
リージャスのFacebookページのタイムラインを見ると、日本語、英語以外の言語の投稿もされていることが分かる。
大久保:ある程度共通したベースのコンテンツがあり、プラスアルファで各国のオリジナルコンテンツが投稿されているイメージなのですね。
川崎:そうです。ただこの運用体制にもメリット・デメリットがあると感じてます。まずメリットとしては、全世界共通のコンテンツがあることで、自分たちですべて1から作らなくてよかったり、全世界でビジネスマンを助けているグローバルな企業であるというリージャスの一貫したカルチャーが発信できたり、海外情報を知りたい日本のビジネスマンの方に喜ばれたりするなどです。
一方で突然英語の投稿が入ってくることで、日本語のコンテンツに慣れ親しんでいる人にとっては少し抵抗を感じさせてしまうのがデメリットと言えます。実際に全世界とプラットフォームが統一された時には、コミュニケーションの一貫性が損なわれた影響か、エンゲージメント等の数値が悪い状態が2~3ヶ月続いてしまいました。
大久保:実際メリットとデメリット、どちらを大きく感じますか?
川崎:今はメリットの方を大きく感じています。やはり弊社はグローバル展開している企業ですので、それをアピールできるという点は非常にメリットとして感じています。
どちらがいいのかというのは判断が難しい部分ではありますが、引き続き運用しながらよりよいカタチを模索していくのだと思います。
ユーザーの段階別に最適なコンテンツを作成
大久保:なるほど。多言語でFacebookページを運用する場合、そういった苦労があるんですね。その他、日本のローカルコンテンツについて気をつけていることはありますか?
川崎:日本国内向けの投稿では、既存顧客向けと潜在顧客向けのコンテンツのバランスを考えて、有益な情報を発信できるように工夫しています。

潜在層にも向けた、異業種交流会に関する投稿
例えばリージャスを良いと思ってくださっている方、ニーズが顕在化しているお客様に対しては、新しい拠点がオープンしたなど、我々の基本的な情報をお渡しすることで反応が得られるかもしれません。しかしながら潜在的なお客様はそもそもリージャスの製品やサービスのイメージができていない場合もあるので、それらの情報を見てもメリットを感じないでしょう。そういったライト層の方が興味を持てるような、軽く読めるような情報も必要だろうと思って投稿のバランスを考えています。
現状の課題とこれからの展開
大久保:引き続きFacebookページは活用されていくということですが、これからこういったことがやりたい、というような展望はありますか?
川崎:今後は効果測定の部分を強化して、体感の効果だけでなく、しっかりと数値面での効果も分かるようにしていきたいですね。
正直、Facebook広告のターゲティングを活用してファンを増やすことはある程度できているのですが、その人たちが本当にお客様になっていっているのかが見える化されていません。そこが大きな課題であり、今後変えていきたい部分です。
Facebookページを開設した前後でお問い合わせのボリュームが増えているのは事実なので、効果はあるのですが、そういったエンゲージメント効果はどうしても見えにくいので、そこをなんとかデータ化して検証するのが、次の戦略として重要だと思っています。
大久保:Facebookの間接的な効果を、より数値化していきたいというところでしょうか。
川崎:そうですね。通常であれば、問い合わせ数は広告での露出に非常に左右されるので、予算削減や効率化を進めていくと、効率は上がっても母数は減ってしまいます。しかしながら現状はそうなっていないので、マーケティング戦略としては非常に理想的というか、良い方向に行っているんですよね。
そういった点からもFacebookページの効果を感じているので、それを数値化して最終的なコンバージョンにどれだけ結びついたのか、仮説だけじゃなくデータとして見ていけたらいいですね。
この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部













