自粛? 通常運転? 自然災害発生時のSNSアカウントはどう振る舞うべきなのか
2019/07/04
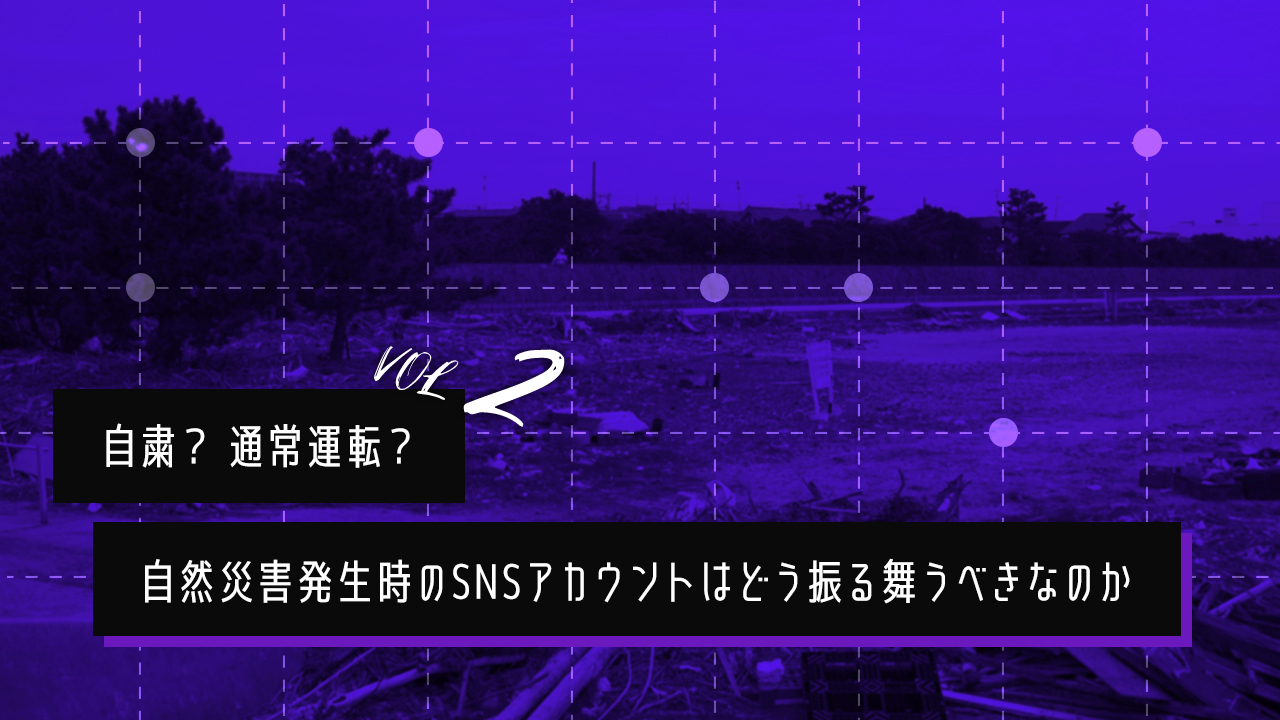
こんにちは、ガイアックスのSNSコンサルタントの重枝(@SGDYSK)です。
今回は自然災害時におけるSNSアカウントの振る舞いについてです。
地震、津波、土砂崩れ、大雨、台風と日本は自然災害の多い国です。また、これらの件数や被害額は近年増加傾向にあるとも言います。そして何より、ソーシャルメディアの登場によって直接現地とつながれるようになった現在、物理的距離のある地域で起こった災害も、身近に感じられるようになりました。
- ■目次
- 世間はどのように受け取るか?
- 緊急事態発生時のSNSアカウント、対応方法の判断軸
- 企業事例から見る、緊急事態発生時のSNSアカウントの具体的な対応方法
- ガイアックス 重枝義樹の過去記事
1. 世間はどのように受け取るか?

「企業は社会の公器」という言葉があるほど、企業がこの社会に深く根差した存在であることは間違いありません。
災害時、大変な思いをされている方がいる中で日常的な発信や、あるいはお祝いやお祭りムードの発信はどうするべきなのでしょうか? やはり自粛するべきなのでしょうか?
実際に何が起こったか、どのような意見があるのかを振り返りながら考えてみましょう。
たとえば、2018年の西日本豪雨の際には、政権与党政治家が参加した「赤坂自民亭」と言われる楽しげなムードの会合が非難を浴びました。積極的に発信したわけではないですが、配慮に欠いた行動と取られたのです。
参考:https://www.asahi.com/articles/ASL7B5W6WL7BUTFK01C.html
一方で、ある地域が大変だからといって他の地域まで自粛ムードに入ってしまったら、経済が回らず、結果大変な地域を支援する余力も削がれるという論理もまた成り立ちます。
参考:http://weblog.horiemon.com/100blog/38454/
また東日本大震災の時も、直後はともかく、しばらく経った後は、お笑いなどのバラエティ番組を視たいという声が被災地から上がってきたということもあります。辛い時だからこそ、笑いなど息抜きが必要だという論理もあります。これもよく分かる話です。
参考:http://www.asahi.com/special/10005/TKY201105200243.html
企業や公人が本当に恐れるのは「不謹慎」そのものというよりも、むしろ「不謹慎狩り」ということもあります。不謹慎狩りとは、世間に自粛ムードのある中、誰かの発言や行為をとらえて「不謹慎である」と非難する行動のこと。
不謹慎の指摘が目的なのではなく、不謹慎を理由に引きずり下ろしたり、マウンティングすることが目的化しているのではないかと推測できるようなケースも少なくありません。
参考:https://ironna.jp/theme/542
その場合、引きずり降ろしたり、自分が高みに昇ることが目的なのですから、本来ならやんわり注意で済むくらいのところを、目的を達するまでしつこく攻撃するので厄介です。
ただし不謹慎狩りを行っていないマジョリティは不謹慎狩りに同調してるでしょうか? ノイジーマイノリティは、サイレントマジョリティよりも見た目上は多く見えますが、実際は逆ということも考えられます。炎上研究でも示唆されている事実です。
社会全体を考えたつもりでも、一部の声の大きい人たちに状況を左右されることは、逆に公共的ではない振る舞いになっているのかも知れません。
参考:http://keisobiblio.com/2016/04/22/atogakitachiyomi_netenjo/
さて、ここまで災害発生時の情報発信に関する様々な事象を見てきました。では実務上は、どうすればいいのでしょうか。
2. 緊急事態発生時のSNSアカウント、対応方法の判断軸

企業は不謹慎狩りを恐れるべきではないでしょうが、配慮を怠るべきでもありません。つまりどのくらい配慮すべきなのかという程度問題になります。
私の今までのコンサル経験からすると、程度を明確にはかる基準を作ることは大変困難です。ただ、問題にあたり考える軸を提供することはできます。軸はふたつに集約されます。
程度をはかるに際しては、次の2軸で考えれば間違いは少なくなるでしょう。すなわち「①当事者性」と「②緊急性」です。
①当事者性
まず当事者性ですが、起こった災害に対して「一義的、あるいは直接的な責任を負っているか」という判断軸です。この答えが「YES」の場合は、通常運転の発信は控えるべきでしょう。
たとえば、災害に対しては当事者あるいは周辺自治体、規模によっては政府や国会議員という話になります。企業では、当該地域に根ざしたサービスを展開しているところで、たとえばホテルや遊園地などです。
では、その地域でも商品やサービスを展開しているが、それ以外でも提供しているという場合はどうすればいいのでしょうか。たとえば、旅行関連業界だったら、ほかの地域についての投稿はしてもいいですが、災害地域の観光情報は控えるべきでしょう。
また、不要不急の広告などは、その地域での配信は控えた方がいいこともあるでしょう。不要不急というのがなかなか難しいところではありますが、その地域の人々にとって、災害時に必要な情報、あるいは災害をおしてでも必要な情報であるかどうかという判断になります。
一方で、当事者から遠いのに、下手に「自分は分かっている」というようなポーズを示す、あるいは当事者に成り代わったような代弁的情報発信も逆効果です。「マイノリティ憑依」というのは逆に不謹慎であるという考え方もあるからです。
参考:http://lite.blogos.com/article/35299/
もちろん、一義的に当事者ではないからといって、配慮が不要になるわけではありません。しかし、通常運転を止めてしまうというのはやり過ぎなことが多いと考えます。例外はもちろんあるので都度検討は必要ですが、適切な距離感での配慮ができている状態であれば大抵は大丈夫でしょう。
②緊急性
②の緊急性ですが、これは地域に関わらずほとんどの企業があてはまることです。今はグローバル時代なので世界にスコープを広げたら事情は変わってきますが、今回はとりあえず日本国内の話です。
たとえば、2018年6月の大阪の震災(https://ja.wikipedia.org/wiki/大阪府北部地震)の直後ですが、都市部で震度6弱ということもあり、被害の状況はもしかすると阪神淡路や東日本の時のような展開になるのでは?という不安がリアルでした。
2019年6月に新潟で震度6強を記録した山形県沖地震(https://ja.wikipedia.org/wiki/山形県沖地震)に関しても同じでしょうな状況がありました。
そのような時は被害状況が明らかになるまで、発信を控えるというのが賢明です。それは、あとで大変だったということが分かった時に非難を受けるからではありません。みなが、必死で正確な情報を集めている時だからです。
そのような時に通常運転の「もうすぐ海の日ですね!」という平時だからこそ楽しい投稿や「弊社は本日で創立100年を迎えました」というようなお祝い発信は心象が悪いでしょう。
しかし、たとえば病気にも、急性期、回復期、慢性期とあるように、災害直後で緊急事態の状況が過ぎれば、通常運転に戻してもいいものがあります。
回復期、慢性期の患者に対してずっと心肺蘇生を試みたり、ICUで絶対安静の手厚い加療はしません。そんなことをしたら、不必要に体力も落ちてしまうでしょう。状況に応じ、日常食に戻したり、仕事を始めることもあるように、情報発信も徐々に日常に戻していきます。
また、2018年の豪雨被害(https://ja.wikipedia.org/wiki/平成30年7月豪雨)に関しては、地震のように一瞬で明らかに大きいものだと分かるわけではなく、ジワジワと被害が広がるということがありました。
これも、病気に例えられます。車にはねられて集中治療が必要だという状況でなければ、進行性の重病でも日常との折り合いを考えながら治療は行われます。状況を逐一確認しながら、通常運転の中でもさらに是々非々で、発信を行なったり、行わなかったりするということが正解になります。
この当事者性と緊急性という2つの軸を中心に考えていけば、不謹慎と非難されることを過度に怖れる理由はないでしょう。次は当事者性と緊急性の観点から、自粛すべきと判断した時、実際にどうするか見ていきましょう。
3. 企業事例から見る、緊急事態発生時のSNSアカウントの具体的な対応方法

まずは、予定していた投稿はいったん見直し、下記の方針での運用を検討すべきでしょう(特にキャンペーンなどは要注意です)。
- A. 非常時の運用に切り替える
- B. 投稿を中止する
Aは災害に対応した投稿を行うということです。具体的事例は後ほど示しますが、災害時に必要な自社の製品やサービスにまつわる情報発信を行ったり、有益な情報を適宜流すということです。
これは当意即妙が求められることでもありますが、企業が社会的責任を果たす機会でもあるという意味では、一種のソーシャルマーケティング(参考:https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossary/detail-11862.html)とも言えます。
Bは文字通り「一旦すべての投稿を止める」ということです。Aのパターンのような即時的な対応ができるリソースがない、意思決定が急にはできない、もともとのアカウントにふさわしくないという企業も多いでしょう。
その場合は、せめて事態の全貌が明らかになるまでいつも通りの運用を一旦停止するなどで対応しましょう。
緊急事態発生時の企業SNSアカウントの投稿例
先ほどご紹介した「A」にあたる、非常時の運用をしている企業アカウントの投稿例をご紹介します。
シャープ
なお念のため、災害時の家電の取り扱い注意点です
・破損した太陽光パネルには触らない
・冠水した製品には通電しない
・停電時は家電のコンセントを抜く https://t.co/IykwUICsBl
— SHARP シャープ株式会社 (@SHARP_JP) 2018年6月18日
タニタ
ニュース映像が視聴できます。余震にお気をつけください。
大阪で震度6弱の地震|NHK NEWS WEB https://t.co/t1Jzoe8kSi
— 株式会社タニタ(涼しい) (@TANITAofficial) 2018年6月18日
au
災害用伝言板・災害用音声お届けサービスの提供を実施しております。下記のURLよりご確認、ご利用ください。
災害用伝言板 → https://t.co/4S1hwvKU2w
災害用音声お届けサービス → https://t.co/10z3uReREq
— au (@au_official) 2018年6月17日
NTTドコモ
災害用音声お届けサービスと災害用伝言板を提供中です。 PC/スマホ⇒https://t.co/JvXmTewDqr iモード⇒https://t.co/cawFJwesVt
— NTTドコモ (@docomo) 2018年6月17日
ソフトバンク
大阪府北部を震源とする地震に伴い、災害用伝言板/災害用音声お届けサービスを提供しています。https://t.co/x2OEhdB04h
— SoftBank (@SoftBank) 2018年6月18日
自社の商品・サービスにまつわる震災時の注意喚起を行うというのは、とても真摯な態度です。ウェブサイトに載せている場合もあるでしょうから、そのリンクシェアでもいいでしょう。
また、自社と直接関係なくても、有益と思われる情報をRTしていることもあります。
このような姿勢こそが多くの企業で打ち出している社会貢献という価値を体現していると言えるでしょう(デマを拡散しないように、オーソライズされた情報をシェアするように気をつけましょう)。
4. ガイアックス 重枝義樹の過去記事
・ビジネスチャンスは今。進行するダークソーシャル化と対応の仕方
・5分でわかるソーシャルメディアマーケティング
・重枝のコラムが毎週読める限定Facebookページのご案内
この記事を書いた人:重枝義樹













