炎上はSNSアカウントを持たなくても起こるし、そもそも予防不可能。そして発生してからが本番
2019/07/25
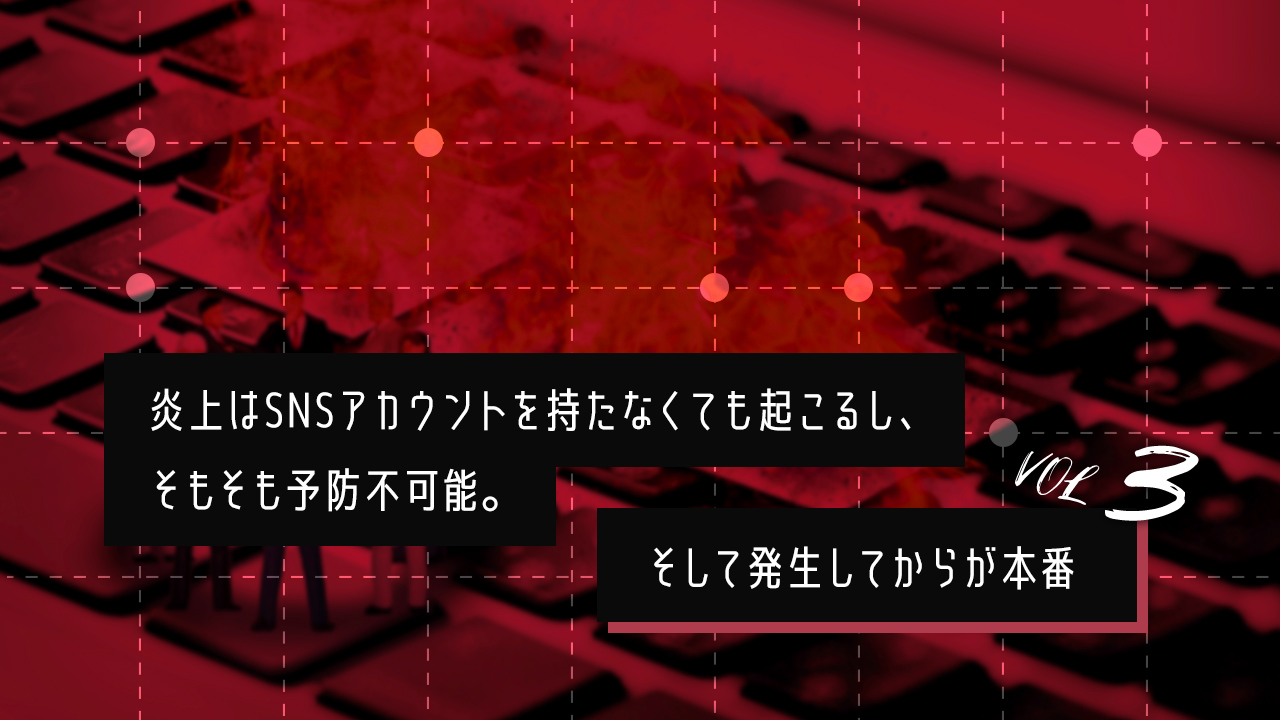
皆さん、ご機嫌いかがですか? ガイアックスのSNSコンサルタントの重枝(@SGDYSK)です。
炎上が相次いでいます。皆さんの体感としてもそうだと思いますし、年々増加していることは数字の裏付けもあります。
2016年まで出ていたエルテス社の炎上件数レポートでも、年々上がり調子でした。
参考:http://chosa.itmedia.co.jp/categories/marketing/86370
NHKの『”ネット炎上” 追跡500日』で示されたデータでも2016年6月から2017年9月にかけて炎上件数はやはり増加しています。
参考:https://www3.nhk.or.jp/news/special/enjyou/
こうなってくると炎上に対する恐怖感が増し、SNSアカウント活用をひかえる向きも出てきますが、それはおすすめしません。
- ■目次
- SNSのアカウントがないことは炎上リスクを大きくする?
- そもそも炎上を避けることが原理的に不可能になりつつある
- そもそも炎上を怖がらなくてよい理由
- 最も恐いのは、炎上への恐怖そのもの
- 価値観が共有されていた時代こそ例外だった
- ガイアックス 重枝義樹の過去記事
1. SNSのアカウントがないことは炎上リスクを大きくする?

実は炎上は、SNSアカウントとは関係なく起こる場合があります。むしろ、関係なく起こる場合の方が多いと言っても過言ではありません。
SNSアカウントを持ったら、そこで失言や誤爆をしてアカウントが炎上するリスクはありますが、持たないでも、不祥事やSNS外での失言、関係者の不適切な情報発信があれば、炎上することは珍しくありません。
実際に今年に入ってからも、SNSアカウントを持っていない数多くの企業が炎上しています。
むしろ、SNS上での発言力を持っていなければ、素早い釈明の機会を損失するとも考えられます。また、公式アカウントがあれば非難がそこに集中してくれるということもあるため、炎上の状況を把握しやすくなるというメリットもあります。
逆に言えば、公式アカウントがなければ、SNS上に拡散したネガティブな投稿を拾い集めて状況把握しなくてはなりません。
つまりSNSアカウントを運用しないことが情報収集を遅らせて対応が後手に回るということがあり得るのです。SNS活用を避けることは炎上対策としてはほとんど意味を為さないどころか、マイナスに働く場合もあるということです。
2. そもそも炎上を避けることが原理的に不可能になりつつある
では、どのように炎上を避けたらよいのでしょうか?
まず企業の不祥事ですが、これはソーシャルメディア上の問題ではなく、全社的な問題です。不正や社員の不品行を完璧に防ぐことなどできるでしょうか?
イエスと胸を張って答えられる企業は少ないでしょう。百歩譲って不正に関しては完璧なコンプライアンス体制を敷けば防げるとして、社員の品行まではとても管理はできないでしょう。
ではSNSアカウントに限らず、メディアでの失言は防げるでしょうか?
たとえば、批判や揶揄、パロディ、ジェンダーなど、明らかに炎上しやすいテーマを避けることは可能です。「男らしさ」や「女らしさ」の強制も、炎上している企業は過去に複数ありましたが、啓発やガイドラインの作成などの対応次第で多くは防止できるでしょう。
しかし、たとえば粉ミルクについて発言すると完全母乳主義の人たちから、毛皮製品の写った画像を投稿すると動物愛護主義の人々から、批判を受けるリスクがあります。マグロやウナギが美味しいとツイートすれば、海洋資源の保護の観点から非難されることだってあり得るのです。
普段からすべてに配慮できる企業はだんだんと少なくなっていくでしょう。炎上したとしても謝ったり、改めなきゃいけないのかも不明です。
よく炎上を避けるために、政治や宗教の話題は避けましょうというアドバイスするコンサルタントがいると聞きます。私はその話を聞くたびに、そんな誰でもできるようなアドバイスにとどまるコンサルだったら辞めてしまえと思ってしまいます。

たしかに「〇〇党には反対する」とか、「〇〇教は危ない」だとか分かりやすいものであれば、それは簡単に防止できるでしょう。
しかしこの複雑な時代状況の中で、何が政治的で、何が宗教的だというとはもはや自明ではないのです。そして政治的な発言をあえて行うということがブランド価値の向上に働くということすらあります。
アパレルブランドGAPの傘下にあり、1994年にカリフォルニア州に最初の店舗を開き、現在ではほぼ全米に店舗を持つOLD NAVY。
同ブランドは、2016年4月にセールの告知をするために異人種家族をモデルとして起用し、キャンペーンツイートをしたところ白人至上主義者から多くのバッシングを受け、アカウントは一時炎上する事態になりました。
しかし、OLD NAVYはそうした主義主張に対して
“We are a brand with a proud history of championing diversity and inclusion. At Old Navy, everyone is welcome,(訳:我々はこれまで多様性を支持してきた誇らしい歴史のあるブランドです。OLD NAVYでは、どんなひとでも迎え入れられます。)”
と反論し、さらに該当ツイートのモデルを担当したプロサーファーのClay Pollioni氏も、
“I’m extremely proud to have taken part in a campaign that not only celebrates our nation’s diversity, but also unites families with multicultural backgrounds and promotes love of all kinds! ,(訳:自国の多様性をただ祝福するだけでなく、多文化的な背景を持った家族を一つにし、あらゆる愛情をプロモートするキャンペーンに参加できたことを本当に誇りに思う)“
と、とても率直に、前向きな発言をしました。
そしてその反論や発言に込められたスタンスに共感を覚えた多くの異人種家族が「#LoveWins」というハッシュタグとともに自身の家族の写真をSNSにアップロードし始めたのです。
その結果、今回の事案と同ブランドのスタンスやストーリーが様々なメディアに取り上げられることになり、同社に対する共感とともに世界中に拡散されるに至りました。批判的な声に屈せず、一貫したメッセージを伝え続ける企業は、共感され信頼されます。
あえて政治的なスタンスを強調することがマーケティングにとって有効なことは珍しくないのです。
日本でもあえて政治的な投稿を行っている企業があります。2019年参院選当日の7月21日に日曜日にも関わらず、従業員に投票へ行ってもらうため全直営店を休業することにしたパタゴニア。地球環境問題解決のための投票を投稿でも訴えています。
#私たちの地球のために投票しよう
気候変動の影響は、既に日本を含む世界の様々な地域・分野で現れています。今後、温暖化の程度が増大すると、深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響が生じる可能性が高まるといわれています。#地球に投票するということの意味
#パタゴニア #voteourplanet pic.twitter.com/YYD6RTapCV
— パタゴニア (@PatagoniaJP) July 10, 2019
炎上するから政治的な投稿は避けましょうというようなアドバイスはパタゴニアのような勇気ある企業には不要です。
仮に炎上が起こっても、彼らにとっては追い風にしかならないでしょう。実際には炎上どころか、多くの共感が集まり、パブリシティの効果も、ブランド価値の向上も達成していると言えます。
3.そもそも炎上を怖がらなくてよい理由
それでも自社が炎上すると、四面楚歌で社会全体から批判されている感覚になるものです。しかしながら、複数のデータから「炎上に実際に参加している人は、全体のごく一部である」ということがわかっています。
例1:メーガン妃に対するヘイト・ツイート
参考:https://www.newsweekjapan.jp/stories/woman/2019/03/720.php
ヘイト・ツイート約5,200のうち7割ほどが、20のアカウントによるものだった事例。
例2:日本国内の炎上に関する調査結果
参考:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/48934
過去一年間に炎上に参加した人々は、ネット人口のわずか0.5%という調査も。
英語ではトロール、日本では炎上仕掛け人と呼ばれるような彼らは、実はマイノリティなのです。もちろん、「炎上は所詮ごく少数が騒いでいるに過ぎないから、気にしなくてOK」とは言えません。見極めるべきは、炎上している理由が「サイレントマジョリティも共感できるものなのか」です。
炎上仕掛人は正義感で炎上を起こしている場合もありますが、その正義感は時に先鋭的過ぎてひとりよがりの場合もあります。また、中には炎上のネタは何でもよくて、ターゲットをやり込め自らの力を示すことさえできればいいという、炎上が自己目的化していると見られるようなタイプもいます。
先鋭化し過ぎた正義感や、自己目的化した炎上は、炎上が目的ではないサイレントマジョリティにとっては当然共感可能なものではありません。共感できるかどうかは、炎上の「ネタ」の部分にかかっているのです。

たとえば、企業が製品に関する不具合を起こしたにも関わらず不誠実な対応をした場合、炎上仕掛け人たちがそこを突いたら、サイレントマジョリティも共感するでしょう。そうなると、炎上仕掛け人たちはオピニオンリーダー的に機能します。
しかし、不具合に対して深く反省し誠実な対応策を打ち出しているのに、そこに無理やり文句を言っていれば、逆に炎上させている側にサイレントマジョリティが悪印象を持つこともあります。そうなるとノイジーマイノリティになるわけです。
サイレントマジョリティは火中の栗を拾いには行きたくないので、よっぽどのことがない限り黙っています。結果として炎上仕掛け人たちの発言ばかりがソーシャルメディアに広がり、あたかも世論のように見えてしまう。しかしそれは真実ではありません。
重要なのは、炎上理由と対応を冷静に見ているサイレントマジョリティに、どのようなイメージを持たれるか。企業が対応すべき相手はこの層であり、「誠意ある対応をすれば理解してもらえる可能性は十分にある」と認識しましょう。
たとえ炎上してしまったとしても、常識的な人々に向けて誠実なコミュニケーションを心がければいい。そう思えば、ソーシャルメディア活用の見通しも、少しは明るく感じられるのではないでしょうか。
4. 最も恐いのは、炎上への恐怖そのもの

誠実なコミュニケーションというのはシンプルな話で、不祥事や失言などの場合は、謝罪、経緯説明、対応策、経過の報告を行なっていくということです。
また、誤解に基づく炎上であれば、逆ギレせずに、淡々と誤解を解く説明をしていきます。
そして、自らの思想信条をつらぬかなくてはならない場合は、毅然とした対応を行うということです。
聴く人は聴いているわけで、炎上が起こったから黙ってしまうとか、隠蔽しようとする、ましてSNSアカウントを削除してしまうなどはあり得ないのです。そんなことをすれば、逆にサイレントマジョリティは「やっぱり悪いことをしてるんだ」という印象を抱く場合もあるでしょうし、何より本当の顧客に向き合う機会を失います。
炎上仕掛け人の方も空気は読みますから、企業が立派に対応していれば、早々に別の炎上ネタに移っていきます。彼らも暇じゃないのです。
炎上したときも慌てずに、批判を受け止めて冷静に検討し、多くの対立する価値を参照し、その上で理路整然と自らの主張を述べ、直すべきところは直し、変えるべきでないところは守る。そんな振る舞いが求められます(だんまりを決め込んだり、一方的な正義を押し付けるような釈明を行う以外は何もせず、鎮火することもありますが、それはたまたまラッキーなだけです。他により大きなネタがタイミングよく現れてくれるかどうかの賭けでしかありませんし、求職者や投資家が企業について情報を調べた際もネガティブな材料になってしまうでしょう)。
自社の立場を明確にする結果として、一定の顧客は失うかも知れません。しかし、対応方法や企業の考えが誠実で納得できるものであれば、炎上を見守っていたサイレントマジョリティ―の支持を得られる可能性も十分にあります。
つまり、炎上を起こさないことではなく、「炎上の対応の仕方」が重要なのです。トラブルの時にその人の真価がわかるというのは、我々が普段経験していることでしょう。そうです、SNSとは社会そのものなのです。
これからの企業には、マーケティングのテクニックや科学も必要ですが、政治哲学のような思考も求められていくでしょう。そしてそれはとりもなおさず、マーケティングやPRの一丁目一番地なのです。
炎上に対して恐れるべきは、炎上への恐れそのもの。企業も個人も、恐れを脇におき、誠実な対応とコミュニケーションをとることが王道だと言えます。
5. 価値観が共有されていた時代こそ例外だった

ここからは蛇足。
さて、当たり前の話ですが、自分たちが常識だと思っているものは他者にとってはそうではありません。そして、別の常識を持つ他者の思想信条に反したかどうかは、その他者の批判を受けるまで気がつかないのです。
性別役割分業がはっきりあって、年齢ごとのライフステージもおおよそ決まっていて、学歴や会社のランクでヒエラルキーのあった過去の時代は不自由でしたが、何が常識かは比較的自明でした。
しかしそれは一定の「質」が担保された「国民」が創出された近代黎明期から総中流社会へと向かった高度成長を経て後期近代に入る直前くらいまでの話。
今後はむしろ、近代以前の、人類がよりバラバラだった時代に再帰的に先祖返りしていくのでしょう。多様性の時代と言われるものは、むしろ人類のデフォルトの姿です。しかしインターネットという文明の利器でつながってしまっているところが、今までの人類とは違うところ。
社会はますます複雑になり、相反する価値観が対立する世界になっていくわけですが、そのような世界で価値中立をうたってもあまり意味がありません。
自分は中立のつもりでも、ほかの誰かにとってはそうでもないことは当たり前です。なぜなら、その中立性の基準も、社会全体で合意したものではなく、自分の中でそう思っているに過ぎないからです。
そのような中で炎上の予防が不可能になるのは致し方ありません。そして、炎上に負けないためには、企業も個人も、自分とは何者かを自らに問うていく時代になったのです。
6. ガイアックス 重枝義樹の過去記事
・自粛? 通常運転? 自然災害発生時のSNSアカウントはどう振る舞うべきなのか
・ビジネスチャンスは今。進行するダークソーシャル化と対応の仕方
・5分でわかるソーシャルメディアマーケティング
・重枝のコラムが毎週読める限定Facebookページのご案内
この記事を書いた人:重枝義樹













